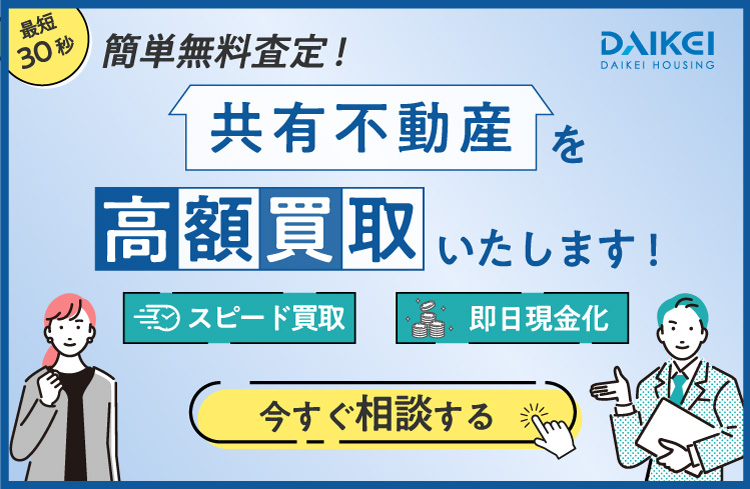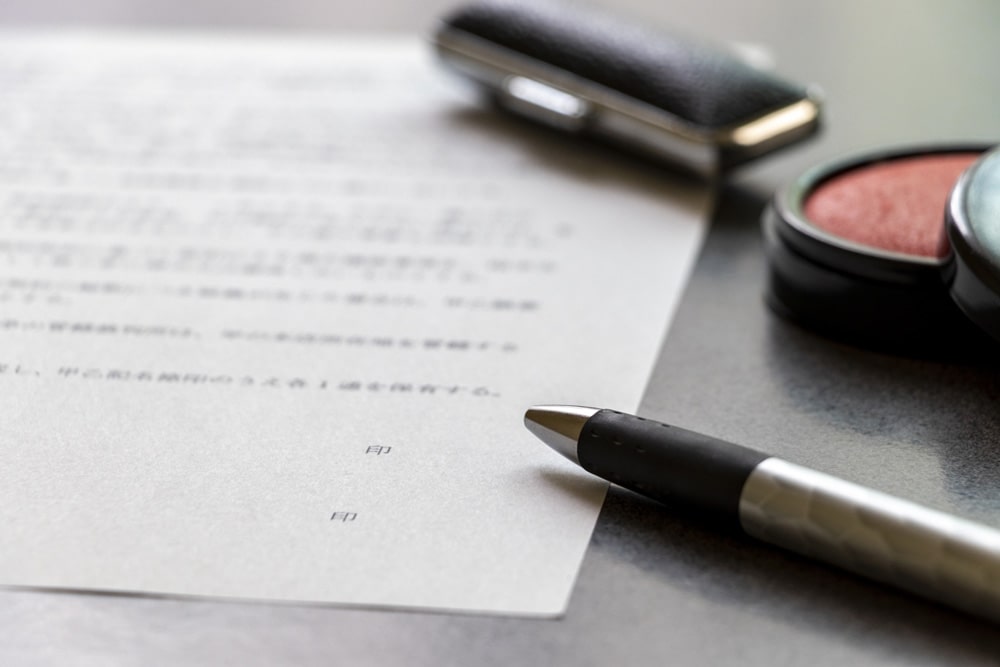【離婚】共有名義の不動産を「売却」or「持ち続ける」メリットとデメリットを解説します!
2025.04.11

目次
 『訳あり不動産』を高額買取
『訳あり不動産』を高額買取
解決します
完全無料
秘密厳守
適正な査定価格
はじめに
離婚は人生の大きな転機ですが、その中でも大きな問題の一つが「共有名義の不動産をどうするか」です。特に、夫婦で住宅ローンを組んで購入した家などは、簡単に処分できるものではありません。
■主な選択肢は2つ
①売却する(売って現金化し、財産分与をする)
②持ち続ける(どちらかが住み続ける、または賃貸に出す)
どちらを選ぶかによって、今後の生活に大きな影響を及ぼします。この記事では、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説し、最適な選択をするためのポイントを紹介します。
◆共有持分の無料相談受け付け中|大慶ハウジング◆
離婚時に共有名義の不動産をどうするべきか?基本的な選択肢
離婚時に不動産をどうするかは、具体的には以下3つの方法があります。
①売却して現金化する
最もシンプルで公平な方法です。不動産を売却し、得た資金を夫婦で分けることで、金銭的なトラブルを避けられます。
■売却の流れ
1. 不動産会社に査定を依頼(現在の市場価格を把握)
2. 夫婦で売却価格を決める(希望額がある場合、すり合わせが必要)
3. 売却活動を開始(内覧対応・広告掲載など)
4. 売買契約の締結・決済(売却金を分配)
■ 向いているケース
・すっぱり関係を断ちたい
・住宅ローンを維持し続けられない
・新たな生活資金を確保したい
②どちらかが単独所有にする(名義変更)
不動産をどちらか一方が相手方より購入し、住み続ける、もしくは賃貸に出す方法です。ただし、その場合はもう一方の持ち分を買い取る資金力が必要となります。
■名義変更の手続き
1. 不動産の評価額を決定
2. 相手の持ち分を買い取る(住宅ローンが完済できない場合、銀行の承認が必要)
3. 登記変更を行い、単独名義にする
■ 向いているケース
・子どものために家を残したい
・経済的に単独で住宅ローンを支払える
・単独名義住宅ローンへの借り換えが可能
■注意点
・持ち分の買い取り費用がかかる
・住宅ローンがある場合、単独で支払えるか金融機関の審査が必要
③ 共有のまま維持する(共同所有)
不動産を売却せず、夫婦の名義のまま維持する方法です。たとえば、賃貸に出して家賃収入を分配するケースなどがあります。*住宅ローンではなくなります。
■向いているケース
・売却すると損をしてしまう(市場価格が低い場合)
・互いに住宅ローンを完済後、売却する合意が出来る
・円満離婚で、管理の合意ができる
■ 注意点
・維持費や税金の負担が発生する
・どちらかが再婚した場合、トラブルになる
・修繕費など維持費の負担割合に関して事前合意が必要
共有名義不動産を売却するメリットとデメリット
■売却する「メリット」
①公平な財産分与が可能
共有名義の不動産を売却することで、得られる売却益を夫婦で分けることができます。この方法であれば、財産分与が公平に行えるため、金銭的なトラブルを回避できます。
例えば、家に感情的な思い入れが強い場合でも、売却によって利益を分けることができ、双方が納得しやすくなります。また、現金で分けることで、今後のお互いの生活の安定も確保できるでしょう。
②住宅ローンの負担から解放される
もし共に住宅ローンを負担している場合、売却によってローンの残債を一括で返済することができます。これにより、今後も残高を気にしながら返済を続ける必要がなくなり、負担を軽減できます。
特に、離婚後はそれぞれが新たな生活を始めるため、共通のローンを残しておくと、経済的な重圧が続くことになりかねません。ローン完済後は、別々に生活をスタートできるのが大きなメリットです。
③新たなスタートを切りやすい
売却することで、不動産に縛られることなく新しい生活を始めることができます。家を売って現金化すれば、引越し資金を得ることもでき、住居の場所や条件を再設定する余裕も生まれます。
また、物理的な縛りが解けることで、お互いの生活がスムーズに進みやすくなるため、心理的にも新たな一歩を踏み出しやすくなります。
■売却する「デメリット」
①売却までに時間がかかる
不動産の売却は、すぐに決まるわけではなく、買い手が見つかるまでに時間がかかることが一般的です。特に、マーケットの状況によっては、希望する価格で買い手を見つけるのが難しくなることもあります。
そのため、売却には時間的な余裕を持って計画を立てる必要があります。急いで売却したい場合、価格を引き下げることになり、期待通りの金額が手に入らない可能性もあります。
②売却価格の折り合いが必要
売却時には、希望売却価格と市場価格にズレが生じることが多いです。もしも市場価格が想定より低かった場合、双方が納得できる価格を見つけるのが難しくなります。
特に離婚後で感情的な対立がある場合、価格についての折り合いがつかず、トラブルになることもあります。このため、事前に不動産市場の動向を調べ、相場に見合った価格設定を行うことが重要です。
③税金や手数料が発生する
不動産売却には、譲渡所得税や仲介手数料など、売却にかかる費用が発生します。譲渡所得税は、売却益が発生した場合にかかる税金で、所有期間や売却価格により金額が変動します。
また、売却に際して不動産会社に仲介を依頼すると、仲介手数料がかかります。これらのコストは意外に高額になることがあるため、事前にしっかりと見積もっておく必要があります。さらに、売却後の税務処理に関する知識も必要になるため、税理士と相談することをお勧めします。
◆【全部丸投げでOK】あなたの持分だけ高値で買い取ります!|大慶ハウジング◆
共有名義不動産を持ち続けるメリットとデメリット
■ 持ち続ける「メリット」
①将来的に不動産価値が上がる可能性
不動産の市場は常に変動しており、現在は価値が低くても将来的に価値が上がる可能性があります。特に、住んでいる地域が再開発されたり、インフラ整備が進んだりすることで、その地域の不動産価値が高騰することもあります。
売却せずに保持しておくことで、将来的に高値で売却できるチャンスを逃さずに済むかもしれません。特に不動産市場が回復したタイミングを見計らえば、より高い利益を得ることができる可能性もあります。ただし下落するリスクもあるのでご注意ください。
②子どもの居住環境を維持できる
離婚後、子どもがいる場合、家を売却すると転校や新しい住環境に慣れる必要が出てきます。しかし、不動産を持ち続けることで、子どもにとっても安定した居住環境を提供でき、転校や生活環境の大きな変化を避けることができます。特に学校や友達とのつながりを大切にしたい場合、家を持ち続けることが大きなメリットとなります。
③売却の手間やコストが不要
不動産を売却する際には、仲介手数料、譲渡所得税、引っ越し費用などさまざまなコストがかかります。また、売却手続きも時間と労力を要します。持ち続けることで、これらの手間や費用を回避できるため、金銭的・精神的な負担が軽減されます。さらに、急いで売却を決断することなく、じっくりと将来の選択肢を検討することができます。
■持ち続けるデメリット
①住宅ローンの支払いが残る
共有名義の不動産を持ち続ける場合、もし住宅ローンが残っていると、その支払いが続きます。特に、収入が減少した場合、ローンの支払いが大きな負担となる可能性があります。
また、元配偶者がローンを支払わない場合、もう一方が全額負担しなければならないことも考えられます。住宅ローンの返済が長期にわたる場合、その負担が生活の安定に影響を与えることもあります。
②元配偶者との関係が続く
不動産を共有している限り、元配偶者との関係が続きます。不動産の管理やメンテナンス、税金の支払いに関しても連絡を取らなければならず、経済的な負担だけでなく、精神的な負担も残ることになります。
例えば、修繕費用の支払いなどについて、双方の合意が必要な場合もあり、管理が煩雑になることがあります。元配偶者との関係が悪化している場合、これがさらにトラブルを引き起こす原因になることも考えられます。
③維持費や固定資産税が発生する
不動産を保持していると、住んでいなくても固定資産税や維持費がかかります。特に、住んでいない場合、管理費や修繕費用も定期的に発生するため、負担になることがあります。
例えば、外部の維持管理や、家の老朽化による修繕が必要になった場合、その費用も負担しなければならないため、無駄な支出が増えてしまうこともあります。売却しない限り、これらのコストを永続的に負担し続けることになります。
◆【共有持分の相談実績3万件以上】|大慶ハウジング◆
後悔しないための選び方と対策
離婚後に共有名義の不動産をどうするかを決めるのは大きな決断ですが、後悔しないためには慎重な判断と適切な準備が不可欠です。ここでは、売却する場合と持ち続ける場合それぞれのポイントを押さえ、最適な選択をするための対策を紹介します。
■売却する場合のポイント
①できるだけ早めに査定を依頼し、相場を確認する
不動産の市場相場は日々変動しており、ご自身の思っていた状況より大きく価格が変わることがあります。そのため、売却を決めたらできるだけ早めに不動産査定を依頼し、相場を確認することが大切です。
特に、住宅ローンが残っている場合は、売却価格がローン残高を上回るかどうかを事前に把握しておくことが重要です。早めに動くことで、市場の変動を的確に把握し、スムーズな売却を目指すことができます。
②売却益を公平に分配するため、事前に弁護士や専門家に相談する
売却後の財産分与に関して、誤解やトラブルを避けるためには、売却前に弁護士や専門家に相談することが推奨されます。
特に、財産分与をどのように分けるか、税金の取り扱い、譲渡所得税など、売却に伴う法的な問題を解決するためには専門家のアドバイスが必要です。弁護士に相談することで、双方が納得のいく方法で売却益を分けることができ、後のトラブルを防げます。
◆【離婚による共有名義不動産の相談実績1万件以上】|大慶ハウジング◆
■持ち続ける場合のポイント
①住宅ローンの支払い能力をしっかり確認する
不動産を持ち続ける場合、特に重要なのは住宅ローンの支払い能力をしっかり確認することです。もしローンが残っている場合、月々の支払いが生活に大きな影響を与える可能性があるため、現実的な支払い計画を立てることが大切です。収入の見通しや生活費を考慮し、無理なく支払える額かどうかを確認し、返済が困難にならないようにすることが後悔しないためのポイントです。
②名義変更の手続きを適切に行い、トラブルを防ぐ
不動産を単独名義にて持ち続ける場合、名義変更の手続きが必須となります。例えば、共有名義から片方の名義に変更する場合や、元配偶者がローンの支払いに関与しなくなる場合など、名義変更を適切に行うことで、後のトラブルを防ぐことができます。
名義変更をせずに放置していると、税金の支払い責任や不動産の管理に関する問題が後々発生する可能性があります。専門家に相談して、必要な手続きを確実に進めることが大切です。
◆【共有持分の相談実績3万件以上】|大慶ハウジング◆
まとめ
離婚時の共有名義不動産は、売却か維持かを慎重に検討する必要があります。
・ 売却するなら:財産分与がスムーズだが、時間がかかる場合も。
・ 持ち続けるなら:住み慣れた環境を維持できるが、維持管理の負担が増える。
どちらの選択肢を選ぶにせよ、将来のリスクを考慮し、後悔のない判断をすることが重要です。
不動産会社や弁護士に相談し、最適な解決策を見つけましょう。
◆【しつこい営業なし!30秒で無料査定】共有持分専門|大慶ハウジング◆